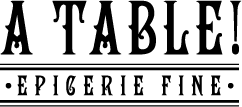政治家で美食家としても知られたサヴァランは「台所の宝石」と称し、作曲家のロッシーニは「キノコのモーツァルト」と呼んだトリュフ。類まれな芳香を持つことで古くから珍重され、フランス料理においても最高級食材として君臨しています。今回は、そんなトリュフの歴史と魅力をご紹介します。
地面の下の木の根っこで育つキノコの一種

日本人にはあまりなじみのないトリュフ(Truffle)。世界三大珍味に数えられる高級食材として名前だけは知っているという人も多いのではないでしょうか。トリュフはキノコの一種で、正確には胞子を生み出す「菌類の子実体」。胞子は子嚢(しのう)という小さな袋の中にあって、形はさまざまです。胞子が育つとトリュフは香りを放ち、菌食性の生き物を呼び寄せます。
その代表がブタで、特にフランスでは古くから“トリュフ狩り”の頼れるパートナーとして活躍してきました。ブタは嗅覚が鋭く、トリュフが大好物。頭もよく、トリュフハンターとしての能力は高いのですが、大好物のトリュフを見つけたら思わず食べてしまうのが難点。トリュフを見つける嗅覚はブタの方が優れていますが、犬は訓練が可能で、主人のためにトリュフを見つけるという使命にまい進してくれます。イタリアではトリュフ狩のお供といえば犬でしたが、フランスでも犬をパートナーとするようになっています。
トリュフの主な3タイプ

トリュフの種類といえば、黒トリュフ、白トリュフ。中でも、産地によって代表的な3タイプとして、「ブラック·フレンチ·トリュフ」「ホワイト·イタリアン·トリュフ」「イングリッシュ(サマー)トリュフ」が知られています。それぞれ香りや風味が全く異なり、使い方も違っています。フランスでは、生産量の多い黒トリュフが主流となっています。
●ブラック·フレンチ·トリュフ
「黒トリュフ」はフランス、スペイン、イタリアなどが主要産地として知られており、特に甘い香りが特徴のフランス産の黒トリュフが有名です。上質なトリュフが採れる産地としてペリゴールやマーニイ地方が知られています。表面はザラザラして赤みがかった黒ですが、成熟するにつれ茶色っぽくなります。切り口の断面は、紫がかった黒檀色で、細かい網目模様が広がります。大きさはクルミくらいのサイズからこぶし大の大きなものもあり、形もさまざまです。秋から初冬にかけて市場に出回り、生のトリュフの豊かな芳香を楽しめる期間は1週間ほどと短いため、旬のフレッシュトリュフは大変高価です。缶詰や瓶詰は通年で手ごろに楽しめます。
●ホワイト·イタリアン·トリュフ

「白トリュフ」は黒トリュフに比べると産地が限られ、生産量も少ないため、より希少性が高いとされています。主にイタリア北部のトスカーナ、ロマーニャ、ピエモンテ地方が優良産地として知られ、特にピエモンテ州アルバ産のものが最高品質とされています。白トリュフのシーズンは晩秋から初春までと黒トリュフより長め。大きさは、小さい卵くらいのものからテニスボールほどのサイズのものが見つかっています。白トリュフは加熱すると香りや風味がなくなるので、料理には生の状態で使います。パスタやリゾット、チーズフォンデュに薄くスライスしたものをトッピングします。黒トリュフ同様、フレッシュなものは貴重なため、基本的にイタリアの市場にしか流通せず、あとは瓶詰、缶詰になります。
●イングリッシュ(サマー)トリュフ
4 月から 8 月にかけて収穫され、通常、黒トリュフと同じ木の下で育ちます。見た目も黒トリュフに似ていますが、香りや風味は全く異なります。イギリス南部のハンプシャー州、ウィルシャー州の高原地帯で見つかっており、イギリスでもかつては盛んにトリュフ探索が行われていましたが、最近はめったに見られなくなったと言われています。
4,000年以上愛されてきた魅惑の香り
トリュフの歴史は長く、古くは紀元前1780年から1760年にシリア東部にあった古代都市で見つかった大量の文書の中に、当時の王が献上されたトリュフの品質について不満を述べている記載が見つかっています。古代ギリシアでは、トリュフは「奇妙な植物」という扱いで、媚薬として使用されていたという記録もあるとか。
4世紀後半か5世紀初頭に書かれたと思われる有名な料理書「料理大全」には、トリュフのレシピが6つ含まれています。中世まではパンやワインのように人の手で加工された食品に価値を置き、自生する野生の植物や地下に生える根菜などは格の低い植物とされていましたが、地中に自生するトリュフは、栽培ができず希少性が高いことから、例外的に高い価値のある食物とされていました。貴族や富裕層の間で媚薬的効果が期待され、人気を博していたといいます。
庶民にも手が届くようになった黒トリュフ

19世紀、ナポレオンの時代になると、ヨーロッパのトリュフ文化の中心はイタリアからフランスに移ります。この時代になると、各地域の特色を打ち出した料理が人気を博すようになり、ペリゴール地方の料理がフランス国内に広まり、ほかの地域にもトリュフが知られるようになりました。
ペリゴール以外でも黒トリュフの産地はありましたが、この地域が一般的に美食で知られていたこともあり、イタリアのピエモンテ産白トリュフに取って代わり、ペリゴール産の黒トリュフの価値が高まっていきました。生産高も上がり、王侯貴族だけではなく、庶民にも手に入る食材になりました。
トリュフの香りを最大限に楽しむ

トリュフの魅力は、なんといってもその素晴らしい香り。そして、「ほかの食材に香りが移りやすい」という大きな特徴があります。生卵を入れたボウルにトリュフを1つ置いておけば、殻を通して中身にまでしっかりと香りが移るほど。運よくフレッシュなものを入手できたなら、お米やパスタなどの近くに一晩置いて、しっかりと香りが移すといいでしょう。
ただし、生のトリュフの素晴らしい香りが持つのは1週間ほど。また、いったん加熱されると、その芳香がほとんど飛んでしまうため、フレッシュトリュフは薄くスライスし、パスタやリゾットなどのトッピングとして使われます。特に卵と相性がいいので、スクランブルエッグやオムレツに合わせるのも人気です。
そのほか、伝統的な料理では、チキンや七面鳥、フォアグラの調理の前に、薄くスライスしたトリュフを載せて、一晩風味を移してから焼くこともあります。秋冬に旬を迎える黒トリュフは、同じく秋からシーズンが始まるジビエのパテの風味づけにも使われ、季節限定の味覚として心待ちにしている人々も多いようです。
もしフレッシュなトリュフに巡り合うチャンスがあれば、ぜひその香りを心ゆくまで堪能を。日本でも人工栽培の研究が進んでいるので、日本でももう少し身近にトリュフを楽しめる日が来ることを期待したいですね。
<参考文献>
「トリュフの歴史」ザッカリー·ノワク著 富原まさ江訳(原書房)
「キノコとトリュフ」ジャッキー·ハースト、リン·ラザーフォード著、中川晴子訳(ソニー·マガジンズ)